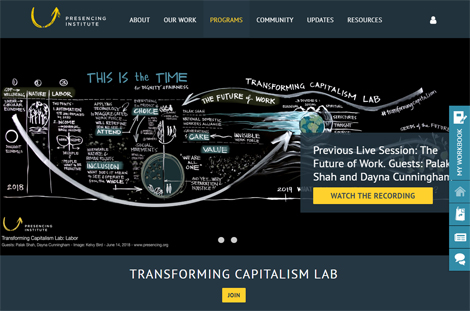U理論のWEBに資本主義を超える新しい経済の試みとしてアズワンの活動が紹介
今、世界が注目する「U理論」。主にマネージメントの手法として脚光を浴びていますが、実は、資本主義を変革し、新たな社会を創造する理論として研究されているものです。
世界的に知られるU理論を提唱しているのは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のオットー・シャーマー博士たちが主催する、“The presensing Institute(プレゼンシング・インスティチュート)”です。そこでは本来の人の生き方や社会、すべての人、人以外のすべての存在、将来世代も含めた、すべての幸せに繋がる新しい経済システムを足元から各地に創出しようとしています。
そのプロジェクトの一つ、資本主義を超えてすべての存在の幸福のための経済を創出するためのプラットフォーム「Transforming Capitalizm Lab(トランスフォーミング・キャピタリズム・ラボ)」の中で、生きた事例として、 アズワンネットワーク鈴鹿コミュニティの 「一つ家計の経済 One Household Economy in city」が紹介されました。
“The presensing Institute(プレゼンシング・インスティチュート)”との出会いは、そのコアメンバーの一人、エコノミスト、Julie Artsさんが、人間性にかなった新しい方向の経済を創出しているところはないかと事例を探して来日していた2017年に、セブンジェネレーションの宇佐見代表から紹介されたことがきっかけでした。

The Presencing Instituteに紹介された、 英文のページはこちらです。
https://www.presencing.org/#/transforming-capitalism-lab/gallery/one-household-economy-in-city
「U理論」とは、マサチューセッツ工科大学のオットーシャーマー博士が体系化した手法で、経営学に哲学や心理学、認知科学、東洋思想まで幅広い知見を織り込んだ他に類を見ない理論と言われています。
今日、私たちは、ますます複雑化する社会の中で、世界規模に至る多くの問題を抱えたままです。気候変動、経済格差、貧困、戦争など、誰も望んでいないにも関わらず、その解決策も軌道修正も出来ずにいます。U理論は、「過去や偏見にとらわれず、本当に必要な“変化”を生み出す技術」として今世界的に注目されつつあり、多くは行き詰まるマネージメントにイノベーションをもたらす手法として脚光を浴びていますが、U理論を提唱する「学習する組織」では、資本主義を変革し新たな社会を創造する理論として研究されているのです。
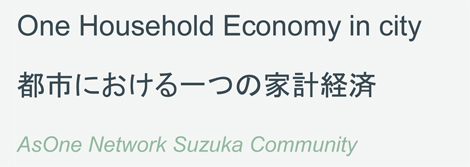
あなたのプロジェクトの背景にある主たるビジョンは何ですか?
アズワンネットワークの主たるビジョンは、「一つの世界」を実現することです。そこには争いはなく、だれも取り残されることなく、誰でも、さらに人間だけでなく人間以外のすべてと、さらに将来世代を含めた存在と調和してその人らしく生きることができる世界です。アズワンの名前は、ジョンレノンの「イマジン」の「世界はやがて一つになる」に由来しています。
人類は宇宙と名づけられた全体世界の一部分です。その世界の本質は、分けようが無いことと常に変化をしていることです。たとえば日本文化を代表する12世紀の随筆『方丈記』にも「行く川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」とうたわれているように。人間は、時間と空間に限定された、生命の乗り物とでもいうような、一つの現れです。
ですから、人類は本来、すべての存在と一つに繋がり、柔軟に平和に生きられる存在であることは明らかです。それにもかかわらず、「なぜ人間はすべてと調和して生きることが出来ないのでしょうか。それが人間の本当の姿でしょうか?」
アルバート・アインシュタインは以下のように述べています。
「私たち人間は、私たち自身および思考や感情を、私たち以外の世界から切り離されたものとして経験している—-しかし、これは人間の認識(の限界)に由来する視覚的な妄想の一種なのだ。この妄想はある種の牢獄のようなもので、ごく個人的な欲望や、ごく周囲にいる限られた人たちに対する愛情に私たちを縛り付けてしまう。」
私たちアズワンネットワークは、そうした認識の限界からくる盲信が人類をミスリードし、他者に対して対抗的なフィクションを生み出し、それらが事実・実際であるかのように固定されていると考えています。たとえば、ポランニーが指摘した「Commodity fiction (商品化のフィクション)」–お金を得るための道具として世界を見る価値体系—お金や交換や所有等で、これは現状のパラダイムの根本問題です。それらのフィクションをベースにして、環境、社会、経済、人間性すべてに亘る計り知れない破壊と引き換えに、資本主義社会は維持されてきました。
人類には客観的な事実・実際に基づいた新しい物語が必要です。それにはまずフィクションをフィクションとして認識し、客観的な事実実際を認識する方法を学ぶことです。ほとんどの個人の世界観や思考は、それぞれの社会における価値体系によって形成されます。人間と社会と環境は、互いに関係しあって存在する一つのものです。以上のことから、現在の主流の価値体系の海に浮かぶ、Commodity Fiction(商品フィクション)のない島のような存在として、私たちは2001年から社会実験としてのコミュニティづくりに焦点を合わせてきました。
そこでは、人々はフィクションへのとらわれから解放され、心豊かに生きようとしています。それぞれの多様な持ち味や能力を育て、地球上のすべてにとっての永遠の幸福と繁栄をもたらそうとしています。理論ではなく、実際の人間を観察することによって、人間問題の根本課題が解決されて取り除かれ、人間性と社会の実際と本質が探究され続け、明らかにされていくとき、たとえその規模が小さくても、人間の可能性を証明するものとして、一つの世界がそこに出現するでしょう。
誰が、何を、どこで、どのように行われているか、プロジェクトの具体的な詳細を説明してください。
アズワンネットワーク鈴鹿コミュニティの63人のコアメンバーと、44人のサポートメンバーが本来の組織とその運営をサイエンズによって実現しようとしています。サイエンズについては、組織的な実践の項目を参照)
*しあわせを目的としたコミュニティビジネス:
Suzuka Farm Co.,Ltd.,と手作りの弁当製造と配達会社(おふくろさん弁当)が鈴鹿市や近隣の市でよく知られています。
*お金の交換の無い内部経済:
「コミュニティスペースJOY」では、米や野菜、果物が鈴鹿ファームから、そして調理されたお惣菜が弁当屋から届きます。日用品やアルコールなどは外で購入されます。ジョイの93人のメンバーはそれらを自由に持って行くことができます。本や自動車、家具、また散髪や機械の修理などの技術もお金なしでシェアされます。70代のメンバーも含めて、すべてのメンバーがSNSを使い、情報に自由にリンクできます。もう一つの内部経済の試みは、「一つの家計経済」ですが、63人のコアメンバーとその家族が、所有なしで、暮らしを自由に発展させようとしてきました。
これまでの最大の成果は何ですか?
2001年から鈴鹿市の中央部に社会実験の場として、コミュニティを運営してきました。その弁当会社「おふくろさん弁当」は2018年現在、一日当たり1000食を販売しています。またその運営方法が、ホラクラシーの一種として最近メディアに紹介されました。また内部経済では、「コミュニティスペースJOY」が93人のメンバーによってお金の交換なしで経営され、並行して、「一つの家計経済」が63人のコアメンバーとその家族によって、所有なしで始まっています。
どんな個人的な実践が、現状のパラダイムからブレークスルーすることを可能にしましたか?
鈴鹿ファームの一人の若者が彼の本心を表明したことから始まりました。それは、コミュニティづくりに専心しているコアメンバーたちに、一番いい野菜を食べてほしいというものでした。「人間が米や野菜を作っているのではない。私たちは現状ではそれらを売ることで利益が必要だ。しかし実際には自然の力で米や野菜が育っていく。」その若者と仲間たちが、2013年に「ジョイ」をつくりました。
どんな組織的な実践が、この成果を現実のものにさせましたか?
鈴鹿ファームは、2010年からサイエンズ研究所と「定例研究会」を始めていました。そこで先ほどの若者が自分の本当の願いを自身の中に見出し、飾らずにその思いをみんなの中に出して、他のメンバーがそこに参加をしていきました。彼らはまず目的を明らかにし、計画を立て、「コミュニティハブ」とともに定例の研究会をはじめ、そこで彼らの計画が目的にあっているか、コミュニティの中でいかに実現できるかを検討していきました。「ハブ」は場所を探したり、経営のための資金的な課題を検討しながら彼らをサポートしました。
「背景」 2004年にコミュニティが人間関係による行き詰まりに直面したとき、あるメンバーたちが人と社会の本来の状態について探究を始めました。その時、サイエンズメソッドが創出されました。サイエンズとは、ゼロからの科学的本質の探究{Scientific Investigation of Essential Nature + Zero}の略語です。サイエンズ研究所が2004年に創設され、またサイエンズを学びながらそれぞれの内面を耕すサイエンズスクールも2006年から始まりました。
以上を通して、私たちは個人の内面の変容と社会的な変容が並行して進展することを経験してきました。
あなたのプロジェクトの社会的影響力が次の段階に進むことを阻んでいるものは何ですか?
私たちは研究し、学んでいきたいと思っています。特に、私たちの社会実験が現存のパラダイムの中で強い影響力を持つために、どのように協力関係を結び、私たちを表現できるかという点に関心があります。しかしながら、私たちが現状の延長線上でどんなに努力しても限界があるのは当然です。まず私たちの現在の状態について冷静な指摘を得ることが必要です。そして世界的な協力関係を実現するために多様な仲間と出会う機会も必要です。
運営の全く新しい次元に向かうために、どんな実現可能な条件が必要でしょうか?
私たちの実態調査をベースにした総合的な理解と協力が、世界全体の動きや情勢を把握している幅広い観点から必要とされています。
私たちは、現在の教育がすべての幸福を実現するための新しい経済を阻害する根本的な課題であると考えています。たとえば、本来人間が作り出した商品化のフィクションにすぎないものを、あたかも現実のことであるかのように信じさせ固定化させるように機能していることです。結果として、巨大な環境破壊や社会の崩落、経済問題や人間性の崩壊などが周囲で深刻な状態で展開しているにもかかわらず、人類は孤立化し、協力して事に当たる関係性を持てない状態に陥っています。他者への強い恐れによって争いが絶えません。
日本や韓国、ブラジルでのサイエンズスクールの参加者を観察していると、私たちは同じ問題を彼らが抱えていることに気付きました。最終的に、その解決方法の一つとして、18年の経験をもとに、サイエンズメソッドを開発したのです。つまり、自分の内面を観察することを通して、人為的なフィクションを、実際にあるものとして思いこまないで、フィクションとして見ることができるような、解決策の一つとして。しかしながら、私たちアズワンネットワークの努力だけでは、地球上に真の人間性にもとづいたパラダイムの変換を実現するにはあまりに小さく弱々しいです。世界中に強い影響力を持てるような、よい仲間が必要であることは明らかです。
このプロジェクトから、あなたが個人的に学んだ一番重要なことは何ですか?
私が学んだ最も大事なことは、私は心から人間を愛しているということ、そして社会づくりは、人間の幸福には必要不可欠であるということです。私はサイエンズをここで共に学びながら、次第に心の奥底にある、他者に対する強い恐れに気がつくようになりました。内面に「やらなければならない」という考え方がたくさんあるのです。現状の社会の価値体系に覆われながら育ってきた経過の中で、私の記憶の中で、「~すべきだ」とジャッジされることへの恐れからくる結果です。それで私は、その都度その都度、自分の内面に問いかけるようになりました。何が人間(私)の作ったフィクションだろうか?何が客観的な実際だろうか。何がその本質だろうか。私はコミュニティの自由で安心できる社会気風の中で、こうした問いを続けることができ、私の本心を見つけることが出来るようになりました。2年前にGlobal Ecovillage Networkという国際的なネットワーク組織の日本の代表として選ばれたのですが、そうしたハードワークに、人間性そのものへの疑念が無い状態で専念できることが幸せです。
あなたのプロジェクトのフィールドで、次の5年から10年以内に探究される必要がある、鍵になる疑問や機会は何ですか?
私たちは心から、プレゼンシングインスティチュートのみなさんに私たちの実態を見に来ていただけたらと願っています。そしてもし関心を持っていただけるなら、なにがしかの協力が始まれば大変うれしいです。
私たちのフィールド自身は、まずすべての存在にとっての幸福を目的としたコミュニティのような理想的な環境を実現していくことです。そして、ごく普通の街の中で、次第に資本主義を真の人間性の方向に変容させていくことです。もしそうした社会実験が十分に機能すれば、他の場所に一般化できるカギを見出せるでしょう。私たちにはそのような確固とした戦略が必要です。
*どのように私たちはこの小さな社会的な試みを一般化できるか?
*フィクションに基づいた人間よりの現実から解放され、フィクションを事実や実際と見誤らないで、フィクションとして認識できるような多様な教育的方法を、どのように私たちは開発できるだろうか?